「対話と協調の外交に取り組んだ1年だった」—。この言葉を聞いて、日本の国民は一体何を思うでしょうか。2025年11月1日、前外務大臣である岩屋毅氏が地元・大分で行った記者会見での発言が、今、大きな波紋を広げています。自らが大臣を務めた石破政権下での外交を自画自賛した上で、発足したばかりの高市新政権に対し、「石破政権の熟議の政治を引き継いでほしい」「仮に政権が右傾化すれば、アラートを発せざるを得ない」などと、まるで“ご意見番”であるかのような注文を付けたのです。
しかし、思い出してください。岩屋氏が支えた石破政権は、衆参の国政選挙で歴史的大敗を喫し、国民から明確に「NO」を突きつけられた政権です。その中心にいた人物が、国民の圧倒的な支持を得て誕生した高市政権の「保守的な国政運営」に釘を刺すという構図は、多くの国民にとって滑稽であり、厚顔無恥としか映りません。
この記事では、岩屋毅氏の発言を徹底的に分析し、なぜ彼の言葉がこれほどまでに国民の神経を逆なでするのか、その背景にある「屈辱外交」の実態と、国民が真に求めるリーダー像との決定的な乖離を、鋭く掘り下げていきます。
自画自賛の裏で見失われた国益:岩屋外交とは何だったのか
Contents
まず、岩屋氏が会見で誇った「対話と協調の外交」の実態を冷静に振り返る必要があります。彼が外務大臣として活動した約1年間、日本の外交は本当に前進したのでしょうか。
1. 「対話」という名の屈辱
岩屋氏の在任中、日本は周辺国、特に中国に対して極めて融和的な姿勢を取り続けました。中国による尖閣諸島周辺での領海侵犯は常態化し、邦人が不当に拘束される事案も相次ぎましたが、日本政府からの抗議はいつも「遺憾の意」を表明するにとどまり、実効性のある対抗措置が取られることはありませんでした。
岩屋氏や石破政権が言う「対話」とは、相手の理不尽な要求や行動を事実上黙認し、ただひたすらテーブルに着くことだけを目的とした、中身のないものではなかったでしょうか。中国からすれば、日本は「対話」を求めてくる限り、何をしても強く反撃してこない都合の良い相手と映っていたはずです。結果として、日本の主権は脅かされ続け、国益が損なわれる状況を自ら招いてしまったのです。
2. 「協調」という名の税金ばら撒き
また、「協調」の名の下に、海外へ多額の税金がばら撒かれたことも忘れてはなりません。国内経済が疲弊し、多くの国民が物価高に苦しむ中、石破政権は海外への経済支援を次々と表明しました。もちろん、戦略的な外交においてODA(政府開発援助)などが重要なツールであることは論を俟ちません。しかし、その支援が果たして日本の国益にどれだけ繋がったのか、その費用対効果については極めて不透明なままでした。
国民からは「ただ闇雲に海外にお金をばら撒いて、移民を推進しただけではないか」という厳しい批判が上がっていました。岩屋氏がこの成果を「対話と協調」と自賛するのは、国民感情とのあまりの乖離を示しており、まさに「裸の王様」状態と言えるでしょう。
なぜ今、石破政治の「継承」を語るのか?岩屋発言の裏にある焦り
選挙で大敗し、国民から見放された政権の政治を「引き継げ」と要求する。この常識外れの発言の裏には、岩屋氏をはじめとする旧石破派、いわゆる「親中・リベラル派」の深い焦りと危機感が透けて見えます。
1. 高市新政権への強烈な警戒心
高市早苗総理は、かねてより「言うべきことは言う」という毅然とした外交姿勢を掲げてきました。先のAPECで実現した日中首脳会談では、中国側が最も触れられたくないであろう尖閣問題や人権問題、邦人拘束問題について、臆することなく日本の立場を明確に主張しました。この姿勢は、これまで中国に媚びへつらうような外交を続けてきた岩屋氏らとは真逆のものです。
高市政権がこのまま「保守本流」の国政運営を進めれば、自分たちがこれまで築いてきた(と勘違いしている)中国との「友好関係」が崩れ、自らの政治的立場が失われることを恐れているのです。「政権が右傾化すればアラートを鳴らす」という言葉は、高市総理への牽制であると同時に、自分たちの存在意義を必死にアピールするための悲痛な叫びにも聞こえます。
2. 公明党の連立離脱と維新との連携という「悪夢」
岩屋氏が会見で特に厳しい表情を見せたのは、政権の枠組みに関する質問が出た時でした。高市政権の誕生を受け、長年自民党と連立を組んできた公明党は、その立ち位置が揺らいでいます。一方で、保守政党である日本維新の会との連携が現実味を帯びており、政策によっては「閣外協力」以上の関係に発展する可能性も示唆されています。
岩屋氏にとって、自民党内のリベラル派と連立政権の「ブレーキ役」を自認してきた公明党が力を失い、代わりに保守色の強い維新が影響力を持つことは、まさに悪夢以外の何物でもありません。「公明党の離脱は望ましくない」「維新との連立は閣外協力まで」と焦りを隠さずに語ったのは、自民党がより保守的な方向へ進むことへの強い抵抗感の表れです。彼は、石破政権が続けてきた「各党との丁寧な対話」という名の、野党やリベラル勢力に配慮した政治運営こそが正義であると信じて疑わないのです。
国民の声は「NO!」:ネットに溢れる批判とドン引きの声
この岩屋氏の時代錯誤な発言に対し、ネット上では当然のごとく、批判と呆れの声が殺到しました。
「岩屋さんは黙って指示書読んでから発言したら?」「何で支持率も低く、選挙でもボロボロになった政権のやり方を受け継ぐ必要があんねん」「石破のやり方を壊してくれる期待が今の(高市内閣の)支持率の表れだろ」「コイツらは何をするにも国民目線でなく、大陸に媚びて自然破壊や日本人同士の対立を煽り、外交も負の遺産を残して次期政権を苦しめているだけ」「そして座を降りたら自分達の武勇伝語りを始めて醜いことこの上ない」「前任が注文を付けずに今の内閣を支えるのが自民党。その慣習を超えてまで必死に守るものは何ですか?」
これらのコメントは、国民が岩屋氏や旧石破派の政治家たちにどれほど失望し、怒りを感じているかを如実に物語っています。国民は、彼らが口にする「対話」や「協調」が、国益を損なう「屈辱」と「自己満足」の言い換えでしかないことを見抜いています。そして、選挙という民主主義のプロセスを通じて、その政治に明確なNOを突きつけたのです。その民意を全く理解せず、いまだに過去の亡霊に取り憑かれたかのように自らの正当性を主張する姿に、国民は心底うんざりしているのです。
時代は変わった:国民が求める「強い日本」と高市外交への期待
岩屋氏が理解できていない最も重要な点は、「時代が根本的に変わった」ということです。国際情勢はますます複雑化・流動化し、力による一方的な現状変更の試みが公然と行われるようになりました。このような厳しい現実の中で、かつてのようなお花畑的な理想論を振りかざす「対話と協調」路線が、もはや通用しないことは火を見るより明らかです。
国民が今、政治に求めているのは、綺麗事ではなく、国益を断固として守り抜く「強さ」です。それは、軍事的な強さだけを意味するものではありません。自国の歴史と文化に誇りを持ち、国際社会において主張すべきことを堂々と主張し、理不尽な圧力には屈しないという、国家としての気概と覚悟です。
高市総理や、彼女を支える茂木新外務大臣が見せる外交姿勢は、まさにその国民の期待に応えるものです。彼らがわずか1週間ほどの間に成し遂げた外交の成果は、岩屋氏が1年かけてもできなかった、日本の尊厳を取り戻すための確かな一歩でした。
今後、茂木大臣の外交の成果が具体的に表れてくるにつれ、岩屋氏の外交がいかに無能で、国益を損なうものであったかが、ますます白日の下に晒されることになるでしょう。その時、彼は一体どのような自己弁護をするのでしょうか。心して覚悟しておいた方がいい、と忠告したい気持ちで一杯です。
結論:過去の亡霊は去れ!日本の未来は国民が選ぶ
岩屋毅氏の一連の発言は、単なる一政治家の失言では片付けられません。それは、国民の審判によって過去のものとなったはずの「失われた政治」への固執であり、新しい時代への変化に対する抵抗です。
しかし、もう後戻りはできません。国民は、選挙を通じて明確に未来を選択しました。それは、自虐史観に囚われ、周辺国に過剰な配慮を続ける政治との決別であり、「強い日本」を取り戻すための新しいスタートです。
図々しくも居座り続けた旧石破派のメンバーによって、日本は1年もの無駄な時間を費やしました。しかし、その時間は決して無意味ではありませんでした。国民は、何が間違っていて、何を正すべきなのかを痛いほど学びました。その教訓こそが、高市新政権を支える何よりの力となるはずです。
岩屋氏のような過去の亡霊に、これ以上日本の未来を語る資格はありません。彼らにできる唯一の貢献は、自らの過ちを認め、静かに歴史の舞台から去ることだけです。日本の進むべき道は、もはや彼らではなく、未来を見据える国民自身が決めるのです。
この件について、皆さんはどう思われましたか?ぜひ、コメントであなたの考えをお聞かせください。
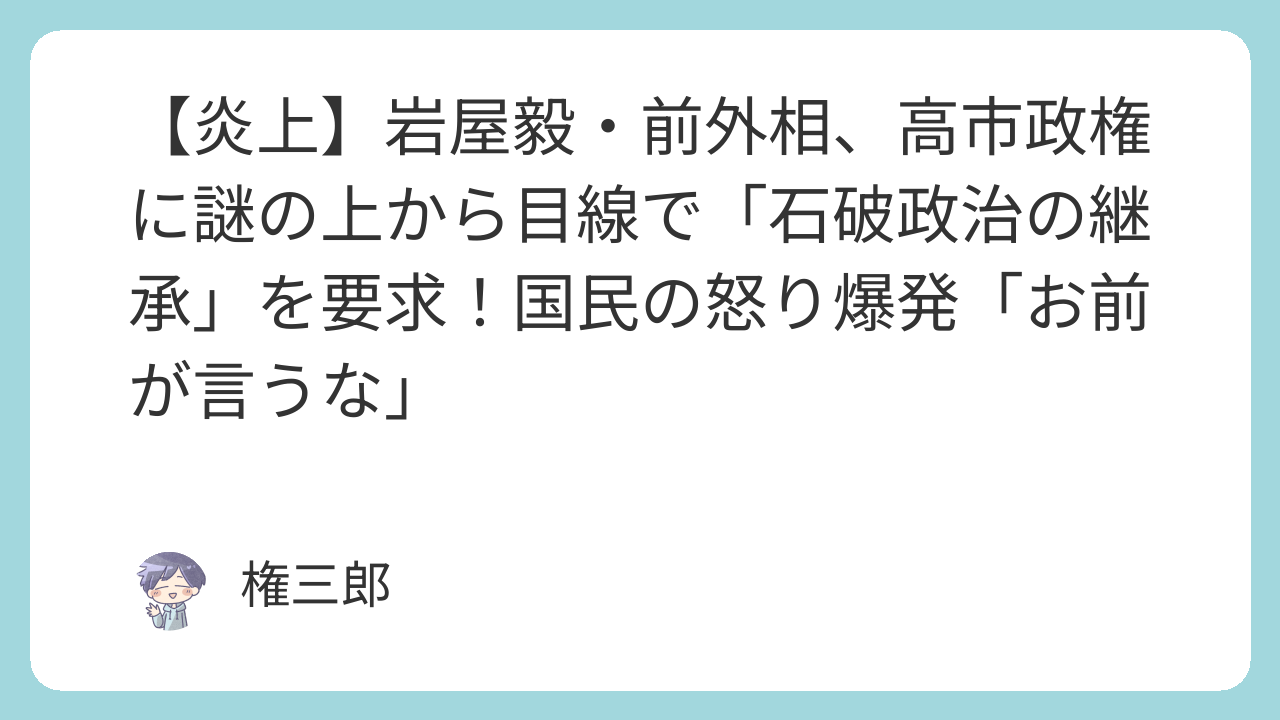

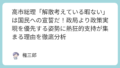
コメント